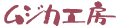北村智恵「風の声」より
写真・岡本 央「郷童」
2023年12月
JR高槻駅前ロータリーの一角に、小屋とも言えるほど簡易で小さな店舗なのに、不似合いなほど立派な、墨跡風の文字で「天然鯛焼」と書かれた、大きな木製の看板が掲げられた鯛焼屋さんがある。その看板が目に入る度に私は、「天然鯛焼?はァ?」と不審に思いながらも店主にその意味を訊ねに行く時間が持てないでいた。鮮魚ならば、天然鯛と養殖鯛がある。だが、鯛の形をしただけの和菓子に、なぜ「天然」が付くのだろう―私の中のB型虫がそこを通る度にうずうずしていた。
その解答を知ったのは、先週、偶然見たテレビ番組の中だった。
NHKの「ドキュメント72時間」という番組で、四ツ谷駅前の「ふたば」という有名な鯛焼屋店頭での収録が放映されていた時だった。店員の説明によると、溶いた材料を流し込み、あんこをのせて再び溶き材料をかけ、合わせ蓋をして一匹ずつ手で裏返して焼くための長い手持ち棒のついた一個一個の鋳型によって焼かれる鯛焼は「天然鯛焼」、そして、広い鉄板の鯛型のくぼみに材料を流し込み、あんを入れたほうと入れないほうを合わせ、同時に何十個も焼けるのが「養殖鯛焼」というのだそうだ。
その日売れた鯛焼は七二〇個。夜、寒い中、閉店間際に駆け込んだ女性が言った。「三十数年勤めてきた会社の長年の部署から、この歳になって営業に回され、馴れない仕事で一日外歩きして毎日くたくた。でも帰りに一日頑張った自分にご褒美で鯛焼買って、食べながら帰るとこのほんのりした甘さと温かさで、よ~しめげずに明日も頑張るぞ~っていう気持ちになれるんです」―と。
職人さんが火の傍で汗を流しながら、心をこめて裏返し一個一個手焼きして作る天然鯛焼が、誰かの日常の一コマでその人の人生そのものを支えることもあるのだということを知って感動し、一度、高槻駅前の「天然鯛焼」を一個買ってみようと思った。自分はあんこ嫌いのくせに―。(ちえ)
2023年6月
大きな病院はいつでも、予約なのに一~二時間待たされるのは当たり前。なので、毎回私は本を持って行く。
どんなに忙しくても私が沢山本を読めるのは、診察前に長時間待たされるおかげなのだ。何時間遅れても苛々しないだけでなく、小説等、此処といういい所で自分の名前を呼ばれたりすると、「えッ?もう私?」と、少々がっかりする時もあるほど。
そんな私が、ある日、本を持って行くのを忘れて、待つ時間、何気なく視力が及ぶ所の貼り紙をボーッと見ていたら、すぐ傍の壁に面白い物を見つけた。横書きで、一行ごとの頭に漢数字が入っている。行頭を縦に読むと「一・十・百・千・万」となる。近づいて読むと「なるほど~」と思うことばかりで思わず手帳にメモしながら、改めて読み返した。
一読(一日に一度はまとまった文章を読もう)
十笑(笑えることを見つける。笑う頻度が低い人ほど
認知症のリスクが高い)
百吸(一日百回深呼吸。一度で10回それを10回)
千字(文字を書くことは認知能力を高める。できるだけ
漢字を使って、日記、手紙、メモを書く)
万歩(心身共にメタボリックやフレイルを防ぎ、認知能
力も高める) 以上高齢者の健康法。〈日本医師会機関紙より〉
…写し終えて、ふと思った。
長歩きや階段を昇るのは運動性発作が起こってしまう重症喘息なので「万」だけ無理だけど、一から千までは私、全部やってるじゃん。だからこんなに元気なんだ~と。(病院でそれ言う?と自分にツッコミを入れて一人笑う。)
そして思った。「今日、本を忘れてきて良かった~それって神の啓示かも!」(また笑い、もう二笑目と自分に満足。)
続いて思った。「ともあれ人生は、おめでたい者勝ち!だから自分は勝ち組に違いない。」と。うふ。 (ちえ)
2022年12月
隣りの家が取り壊され、更地になった。百坪ほどの空き地は今、草一本なく、土肌を見せている。バス通りから2軒目の我が家は、初めての来客に地図を送ったり、電話で説明するときに、これまでずっと言っていた。
「バス通り添いの、赤煉瓦の塀にそって曲がった次の家です」「赤煉瓦の塀の角を、左に入って二軒目です」と。四十数年言い慣れたその「赤煉瓦の塀」がなくなり、その内側に、家の白い壁に映えて玄関に咲く、大きな百日紅の木の、濃い桃色の房のような花の群れは、炎天下でも、門の前を通るとき、佇む者達の目を楽しませ、和ませ、ひととき心を癒してくれる存在だった。
世の御多分に洩れず、私達夫婦も含めて「御近所さん」も高齢化し、家を継ぐべく家族も遠距離、もしくはなかったりして、「空き家」や、売却のための「更地」が増えてきた。バス通りから丸見えになって初めて目にした我が家の横顔?も、心なしか孤独に見える。
隣りに何が建つのだろう?どんな人が来るのだろう?少しの不安と、少しの期待が入り混じった複雑な思いで、バス通りからまる見えになった我が家のゴミ箱にゴミを捨てた今朝、かつてはそのゴミ箱の蓋の上で、安心して日向ぼっこしていた野良猫を、人の目から隠してくれていた隣りの家がもうなくなってしまったのだと急に気付いた。まだ、その家が空き家だったときはベランダの下を折々、野良猫達が雨露しのぐ棲み家にしていたことなどを思い出したり、私の母が、その庭に来るヒヨドリやメジロのために、林檎や蜜柑を輪切りにして並べていたことを思い出したりした。
有難いことに私は、この家に住んで五十余年、本当に「御近所さん」に恵まれ、親切な「お隣さん」と親しく仲良くしてきた。今度は隣りに何が建つのだろう?どんな人が来るのだろう?何が建ってもどんな人が来ても、私は、その人達にとっての「良いお隣さん」になりたいと思っているけれど。(ちえ)
2022年6月
「ちょっと来てみ~」「何?」「裏の家の猫が窓の外でひらひら飛んでる蝶々を、網戸ごしに目で追いかけてキョロキョロしてる。かわいいよ~」と、晩春のある朝、外で洗濯物を干してくれていた夫が、台所にいた私を呼びに来た。勝手口を出てすぐの所、我が家の敷地の東南にあたる角地のちょっとしたスペースはネット・フェンスだけなので、朝日で洗濯物がよく乾く分、雑草ものびのびと花を咲かせている。そこで蝶の舞う姿を遠目で私もよく見るが、裏の家猫が、自分の居る窓の外に飛んできてひらひら舞う蝶を気にして、人と同じように、目で追って遊んでいるというのだ。私がその場所へ行くと、蝶はもういなくて、その猫は近寄った私に気づいて今度は私に視線を向けてじっとおすわりしている。本当に可愛い顔をしていた。「この子の名前、何だったっけ。確か、日本の男の子によくある名前だったなぁ。えーッと、タロー?うーん、ダイスケ?あ、ダイちゃん?」 全く違うのか無反応。それでも一頻り向き合って一方通行の対話(?)をした。さて、戻ろうとして踵を返しかけたとき、足元の草叢にふと目が行った。「えっ?!」とびっくりするような、見たことのない薄黄色の花が二つ、ひっそりと咲いていた。私が自分で植えたものではないので、おそらく亡くなった母が何年も前に植えたものに違いない。晩年数年間は寝こんでいたのでこの花は十年近く経って初めて花をつけたことになる。蘭のような形の花だった。主がいなくなっても置かれた場所でひっそりと、だが凛と咲くその花をとても愛しく思った。与えられた場所で咲き、そこに存在しているだけで、母がこの世に生きたという証しを伝える「役割り」を果たしていると思えたのだった。
そもそも、その花の存在に気付いた「きっかけ」は裏の家の猫である。その子と飼い主にお礼を言おうと思い、その花を一輪、裏の家へ届けに行った。訊くと、その猫の呼名は「しょうちゃん」で、正式名は「しょうご君」だった。(ちえ)